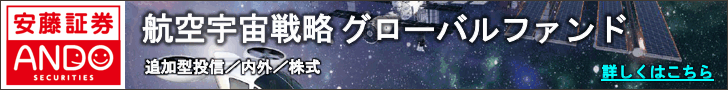広がる支援の輪=助け合う被災住民―ミャンマー地震 2025年04月05日 14時35分

【バンコク時事】ミャンマー中部を震源とする地震の被災地で、住民同士の「支援の輪」が広がっている。離れた地域でボランティアとして支援活動に当たる被災者もいる。震源に近い第2の都市マンダレーに住むシュエリーさん(56)は、時事通信の電話取材に「みんなで助け合っている」と話した。
シュエリーさんは孫を含む8人で暮らす。3月28日の地震で家族にけがはなく、3階建ての自宅も倒壊を免れた。ただ、停電や断水に見舞われ「水が出る家もあるので、住民らで分け合っている」という。自炊できないため、食事は近くの寺院の炊き出しに頼っている。
近所には自宅が崩れたり余震を恐れたりして、路上で避難生活を送る住民もいる。そうした人には寄付された食料や日用品、蚊帳などが届けられている。
シュエリーさんの夫、ミョーウィンさん(58)は地震発生の数日後から、車で約1時間の距離にあるザガイン地域の市街地でボランティアとして活動している。同地域の友人から「支援が十分にない。助けてほしい」と頼まれ、知り合いに声を掛けて集めた物資を運んでいる。シュエリーさんは「必要とされる限り、夫は活動を続けるつもりだ」と誇らしげに語った。
国軍と抵抗勢力の対立のほか、道路の寸断などで物資が十分に届かない地域もある。ザガインに住むキンマウンエイさん(70)は、義理の息子と孫を亡くした。自宅は倒壊し、家族ら計13人が路上で暮らす。現地入りした時事通信の通信員の取材に「寄付で食料と水はある。日よけの毛布や蚊帳、体調を崩した人への薬が必要だ」と訴えた。