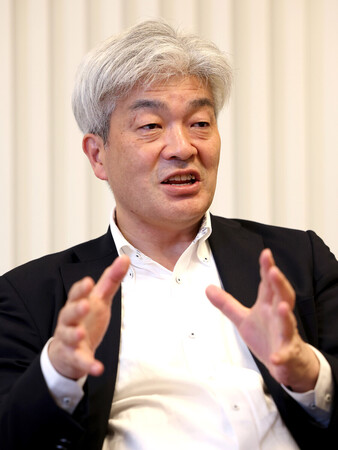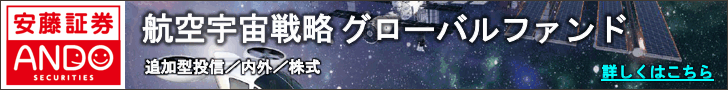「機能不全」G20の行方は=世界経済の展望、識者に聞く 2025年07月15日 16時15分

20カ国・地域(G20)財務相・中央銀行総裁会議が17、18両日(現地時間)、南アフリカ東部のダーバン近郊で開かれる。トランプ米政権の高関税政策によって世界経済の不確実性が高まる中、機能不全がささやかれるG20が協調姿勢を示せるかが焦点となる。元財務省財務官で国際通貨研究所理事長の浅川雅嗣氏と、国際政治に詳しい東京大公共政策大学院の鈴木一人教授に話を聞いた。
◇世界経済に下押しリスク=浅川雅嗣・元財務官
―世界経済が抱える課題は。
米国と中国それぞれ経済の先行きが不透明になっており、大きな下押しリスクだ。トランプ米政権の高関税政策が機能し企業の生産拠点が米国に移っても、高いコストでモノを作ることになり、持続的なインフレ要因となる。大型減税のほか、移民規制強化もインフレを助長する可能性が大きい。中国も個人消費の低迷や少子高齢化によって、以前のような経済成長は謳歌(おうか)できない。
―外国為替相場の見通しは。
正常化を進めたい日本と利下げを模索する米国との間で、金融政策は逆方向を向いており、基本的には円高方向。ただ、トランプ関税で不確実性が高まっている中、日銀も利上げのタイミングはさまざまな要因を考慮し慎重に判断するだろう。
―G20の形骸化を指摘する声もある。
ウクライナ侵攻を続けるロシア、保護主義に走った米国がメンバーにおり、機能しづらくなっているのは事実だ。とはいえ、全く無力というわけではなく、国際課税などG20で議論すべきテーマは残っている。国家主権といえども、協調する努力は必要だ。
―日本が果たすべき役割は。
米国一国で安全保障や自由貿易体制を維持するためのコストを背負い過ぎていることは、考慮しないといけない。日本が音頭を取って、環太平洋連携協定(TPP)のような地域的な枠組みを生かし、多国間貿易体制をサポートすることは検討してもいい。
◇米中抜きの国際秩序構築を=鈴木一人・東京大公共政策大学院教授
―国家間のパワーバランスが変容してきた。
今の国際社会は「力による秩序」によって支配されるようになり、非常に不安定でもろい状態だ。核兵器の脅威があるので大国同士は直接戦火を交えないが、自由貿易が進んだ結果、輸出規制を通じて相手国のサプライチェーン(供給網)を寸断することが可能になった。経済的な相互依存関係が武器として使われるようになってきた。
―トランプ関税が及ぼす影響は。
今の関税政策を真面目にやると、米国内で物価が高騰する。インフレで個人消費が抑制されれば国内総生産(GDP)も縮小し、世界的なリセッション(景気後退)に陥る可能性がある。
―その状況下でG20の存在意義とは何か。
G20はもともと、先進国の集まりに新興国を加えて新たな秩序をつくるという発想だったが、今やロシアや中国といった新興国グループの「BRICS」ですらまとまりを欠く状況だ。ただ、明確な結論が出なくても、各国が参加し、お互いの問題意識を共有することには意味がある。
―日本はどう生き残ればよいのか。
日本は「力による秩序」の世界の中では負け組だ。憲法に縛られていて、エネルギー、食料も輸入に頼らざるを得ない。米国や中国などの大国を除いた国際秩序をつくる発想が必要だ。オーストラリアやカナダ、韓国などとは価値観を共有しやすいだろう。
その他の写真