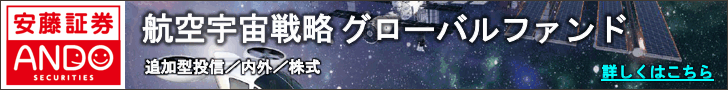「手当拡充」「無償化」で負担減=少子化対策、財源に課題―「深掘り・日本の課題」【25参院選】 2025年07月15日 14時11分

出生数が昨年、初めて70万人を下回り、少子化に歯止めがかからない。そんな中、各党は参院選で児童手当の拡充や教育の無償化などを公約。子育て世帯の負担を軽減し、産み育てやすい環境をつくるとアピールする。一方、対策に必要な財源の議論は尽くされておらず、実現に課題も残る。
◇迫る「ラストチャンス」
政府は、若者が急減する2030年代に入るまでを「少子化を反転させるラストチャンス」として、23年に「こども未来戦略」を策定した。児童手当の拡充や多子世帯の大学授業料無償化、親の就労を問わず保育所を利用できる「こども誰でも通園制度」といった施策を「加速化プラン」に盛り込み、対策に着手した。
今年6月に公表された24年の出生数は68万6061人で、前年から4万人減少。1人の女性が生涯に産む人数を示す合計特殊出生率も1.15と過去最低を更新し、厳しい状況が続く。政府関係者は「出生数のV字回復は相当に難しい。まずは減少スピードを緩やかにすべきだ」と強調する。
参院選で自民、公明両党は、加速化プランに位置付けた各施策を前進させるほか、日本維新の会を含む3党で合意した高校授業料の無償化に取り組むと訴える。
野党は、加速化プランの内容を超える施策を掲げる。児童手当などの給付に関し、立憲民主党と国民民主党は子どもが18歳になるまで月1.5万円、れいわ新選組が高校卒業まで3万円、参政党が0~15歳に10万円を支給すると主張。立民や維新、国民などは0~2歳児の幼児教育の無償化も公約した。
大学授業料は、立民が国立大の無償化と私大の負担軽減を打ち出した。共産党は授業料を半減し、無償化を目指すという。また、多くの与野党は学校給食費の無償化も盛り込んだ。
◇支援金、廃止論も
与野党とも対策の推進・拡充で一致するが、財源で隔たりがある。政府は加速化プランの実施に向け、公的医療保険に上乗せして徴収する「子ども・子育て支援金制度」を26年度から導入する予定だが、立民と国民は廃止を唱える。立民は日銀が保有する上場投資信託(ETF)の分配金収入、国民は「教育国債」の活用を提案するものの、政府・与党は安定財源となるのか疑問を呈する。
支援金はSNS上で、子どもを持たない人に恩恵がない「独身税」だとやゆする向きもある。三原じゅん子こども政策担当相は記者会見で「子どもは社会保障の担い手となる。メリットを享受するのは全ての世代で、独身税と言い換えるのは間違っている」と反論する。
ただ、財源は国民の「痛み」に直結する話題だけに、参院選で議論は深まっていない。将来世代につけを回す事態になれば、少子化を加速する要因となる可能性をはらむ。
◇結婚のハードル下げる政策を
鎌田健司・明治大准教授(人口学)の話 出生率の低下は、未婚化や晩婚化といった結婚行動の変化でほぼ説明ができる。特に日本を含む東アジアでは、結婚してから子どもを持とうとする考えが一般的で、男性に稼得能力が求められているのが実情だ。経済や雇用環境の改善で、若い世代の雇用が安定し、結婚・出産前後で就業継続が可能な状況を達成することで、結婚のハードルを下げることが重要だ。
国際的な研究成果では、児童手当のような現金給付に出生率を向上させる効果は一時的もしくは見えにくいとの結果が出ている。参院選では多くの政党が学校給食費などの無償化を掲げているが、現金給付ではなく、現物給付で無償化が進むと負担感はだいぶ軽減される可能性がある。
子どもは2人持ちたいと考える夫婦が多い中、追加出生の期待に訴え掛ける政策かどうかが重要だ。今年度から多子世帯の大学授業料の無償化が始まったが、追加出生への期待増に寄与しているのか検証が待たれる。また、不妊治療や生殖補助医療への助成は晩婚化が進む中で、直接的な出生促進政策として重要性が増している。