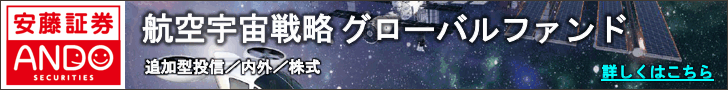誰も得しない危険な判断=イラン・識者談話 2025年09月28日 15時27分

松永泰行・東京外国語大教授(国際政治)の話 2018年に米国が一方的に核合意から離脱し、イランと経済取引しないよう各国に圧力をかけてもイランは耐えてきた。「外圧」で国民生活に影響が出ると、かえって社会の一体感が増す側面が強く、妥協は見込めない。誰も得をしない制裁復活だ。国連安保理がイランの「落ち度」を認定したことになり、6月にイランを攻撃したイスラエルの再攻撃を容認することにもなりかねない。危険で無責任な判断だ。
今回発動された制裁は1991年にイラクに科されたのと同等で、安保理が科せる最大規模の措置。軍事行動の一歩手前だ。解除は困難で、イランの体制を変えるための戦争をしない限り、半永久的に続く。制裁破りの監視にも膨大な手間がかかる上、ほとんど効果はないだろう。
6月の米・イスラエルの攻撃で損壊した核施設の再建には、制裁の影響でかなり時間がかかる。イランの高濃縮ウラン製造は国際社会との「交渉材料」を得るのが目的であり、核兵器の開発はしないだろう。政府は核拡散防止条約(NPT)離脱を表明しておらず、今後も国際原子力機関(IAEA)の査察対象ではある。しかし、核合意でイランが受け入れてきたレベルの査察は不可能になるため、有効性は皆無になる。