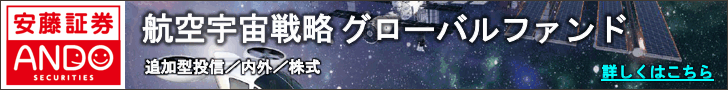選挙介入、監視・規制を強化=政府、偽情報対策で法整備も 2025年08月02日 14時06分
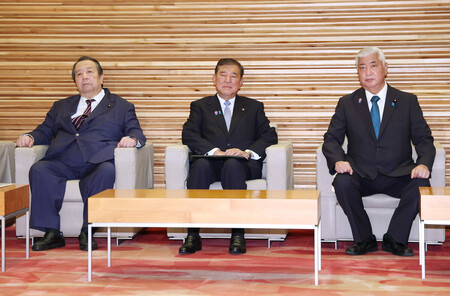
政府は外国勢力による選挙介入を防ぐため、監視能力や規制の強化に乗り出す。一元的に対処する体制を整え、法整備も視野に入れる。7月の参院選ではSNS上で偽・誤情報の拡散が問題となり、外国勢力の関与が指摘された。内閣官房の「国家サイバー統括室」を中心に検討し、課題を洗い出す。
平将明サイバー安全保障担当相は1日の記者会見で、選挙介入について「民主主義に対するリスクだが、明確に対応するところがない。司令塔をつくる必要がある」と述べ、対応の具体化を急ぐ考えを示した。
選挙介入は、他国の世論や政策決定に影響を与えるための情報操作やプロパガンダ活動である「影響工作」の一種。民主主義国家の選挙を狙い、偽・誤情報や過激な言説をネット上に広めることで、社会分断による政治体制の不安定化や、特定候補・政党の勝利を図るとされる。明治大サイバーセキュリティー研究所の斎藤孝道教授は「軍事戦略の一環だ」と指摘する。
2016年の英国の欧州連合(EU)離脱国民投票や同年以降の米大統領選、24年の台湾総統選を巡り、ロシアや中国の関与が疑われた。
日本では先の参院選で、SNS上で「ボット」と呼ばれる自動投稿プログラムによるとみられる不自然な情報拡散が問題となった。ロシアの関与が指摘されたサイトとつながる複数のX(旧ツイッター)アカウントが凍結される事態も発生。青木一彦官房副長官は選挙期間中の記者会見で「わが国も(外国による)影響工作の対象になっている」との認識を示した。
政府は現状、内閣官房や外務省、防衛省などが情報収集・分析に当たり、総務省がSNS運営事業者に不適切投稿への対応を要請する。脅威が深刻化する中、省庁横断的な対応が必要となっている。
問題のある投稿の削除やボットアカウントの排除など、遮断措置の構築が課題となる。ファクトチェックをどう行うかや、偽・誤情報ではない「外国人は敵だ」などの過激な主張をどこまで規制するかの線引きは難しい。憲法が保障する「表現の自由」に配慮した法体系が必要で、制度設計は難航が予想される。
政府関係者は「SNS事業者にどの程度の義務付けを行うかなど、検討事項は多岐にわたる」と指摘。「能動的サイバー防御」の司令塔として7月に発足した国家サイバー統括室を中心に、参院選での「介入」事案や他国の制度を調べ、論点をまとめる考えだ。