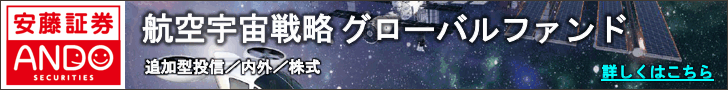「早期のチベット解放を」=故郷に両親残す亡命政府職員 2025年06月27日 15時05分

【ダラムサラ時事】「21年以上、家族に会える日を待ち続けている。チベットが早く解放されることを願っている」。インド北部ダラムサラ。チベットの歴史や文化を伝える博物館で、チベット亡命政府職員の女性(30)は目に涙をためて打ち明けた。
目の前にはチベットで1959年に起きた動乱以降、ダライ・ラマ14世をはじめ大勢が故郷を逃れた経路を示す図がある。女性も2003年、チベット東部の集落から他の32人と共に国境越えを目指した。その中に家族はいなかった。
中国当局による監視の目をかいくぐるため、移動は主に夜間。幼かったが「真冬に首まで漬かった川の水の冷たさを忘れることはできない」。ネパールを経てインドにたどり着いたのは、出発から約1カ月半後。その過程で死者や行方不明者も出た。
亡命以来、チベットに残った両親とは会えていない。「来た道をたどって戻ろうとも考えた。家族や故郷を思い、毛布の中で声を殺し泣いたこともあった」と振り返る。
中国チベット自治区でもある故郷では、共産党政権によってダライ・ラマの写真掲示が禁じられ、女性はインドに来て、僧侶として実在していることに驚いたという。故郷の学校では中国語の学習を強制され、固有の歴史や文化を教わることはない。「中国はチベットという国を消し去ろうとしているが、どんな政府でも不可能だ」と語気を強める。
女性を送り出した家族は「より良い教育を受けさせ、チベットの文化や遺産を守らせたかった」のだという。亡命政府の援助で教育を受けた女性は、インド最高峰の大学で学位を得た後、職員として働くと決意。「今度は自分の番。チベットの大義のために働き、それを次の世代に伝える責任がある」と力強く語った。